片付けを始めるときに、一番大変なのは「モノの多さ」よりも「家族との意見の違い」かもしれません。
特に親世代の持ち物は本人にとって思い入れが強く、私たちの感覚で「不要」と決めてしまうと揉め事に発展することも…。
 夫
夫我が家もコンテナ倉庫を片付けたとき「残す?捨てる?」をめぐって話し合ったよね。
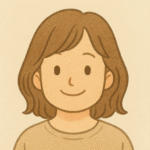
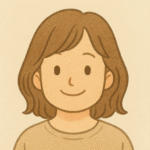
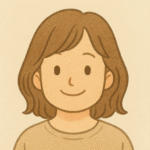
ゆっくり気持ちに寄り添うことができたから「やってよかった」と思える体験になったんだね。
今回はその経験を交えつつ、家族と揉めない片付けのコツをご紹介します。
これは単なる片付けにとどまらず、親世代の「終活」にもつながる大切な視点です。
親・義実家の片付けが難しい理由
モノへの思い入れが強い
私たちの親世代(70代以上)は、戦後の物が少ない時代や高度成長期を経験しています。
そのため「まだ使えるものを捨てるのはもったいない」「いざという時に役立つかもしれない」という気持ちが自然と根付いています。
例えば、使い古したタオルや空きビン、壊れた電化製品の部品やねじ類なども、「何かのときに使えるから」と残してあることがよくあります。
私たち世代から見れば「不要」に思えても、親世代にとっては生き抜くために身についた習慣なのです。
世代間の価値観の違い
私たちは「便利で新しいものが簡単に手に入る」時代を生きています。
だからこそ「壊れたら買い替える」「同じ物を複数持つ必要はない」と考えます。
一方で親世代は「ひとつの物を長く使う」「持っていること自体が安心」と感じやすく、同じ物でも手放す基準がまったく違います。たとえば、古い食器や着物、今では使わない家具なども「高かったから」「思い出があるから」と残しておきたいのです。
つまり「使う/使わない」ではなく「価値がある/ない」というところに判断基準があり、その価値観の違いが大きな壁になるのです。
片付け=終活を意識する|抵抗感
もう一つ大きいのは「片付けは自分の死後を意識させる行為」という点です。
「片付けよう」と声をかけただけで「もう死ねってこと?」と受け取られてしまうケースもあります。
これは決して意地を張っているわけではなく、「自分がいなくなった後」を考えるのは誰にとっても怖いことだからです。
そのため、片付けの話題を避けたり、強い抵抗を見せたりするのです。
ポイント
親世代が片付けに消極的なのは「頑固だから」ではなく、
- 「もったいない精神」
- 「価値観の違い」
- 「死後を意識したくない心理」
これらが背景にあると理解することが大切です。
ここを理解できると「なんで捨てないの!?」とイライラする気持ちが少しやわらぎ、揉めない片付けの第一歩になります。
家族と揉めない片付けのコツ
相手の気持ちを先に聞く
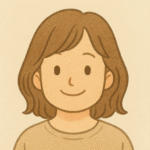
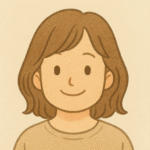
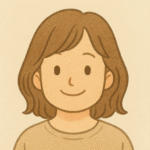
「邪魔だから捨てよう」ではなく、「これどうする?」と問いかけて
本人の思いを尊重することが大切です。
私は「これどうしますか?」とすべて義母に確認していました。
初めはほとんどのものを「取っておきたい」と答えていた義母ですが、数日後に「今後使う予定がありますか?」と具体的に聞き直すと「処分していい」と返事が。
もちろん使えそうなものは義母の了承を得てメルカリに…。



使わないけど、なんとなくとってあるものが多かったわね。
捨てるのはもったいないけど、メルカリに出す…って考えたら気が楽になったわ。
そうやって必要なものを選んでいくうちに、義母の判断のスピードもどんどん速くなっていきました。
一気にやらず「小さく区切る」
倉庫や押し入れを一度に片付けようとすると、体力的にも精神的にも負担が大きすぎます。
「今日はこの引き出しだけ」「この棚だけ」と小さなゴールを決めると、達成感もあり揉め事も減ります。
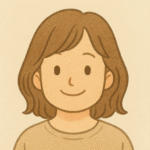
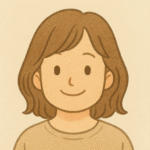
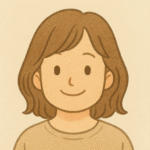
倉庫には大量のものが入っていたので、処分場に持っていく日を決めてから少しずつ準備をしました。
おかげで当日は半日ほどで片付けを終わることができました。
「残す理由」を大切にする
片付けの基準は「使う/使わない」だけではありません。
「思い出として残したい」「気持ちが落ち着く」といった感情的な理由も尊重することが必要です。
義母も義祖母の古いアルバムを見つけて、「どうしようか」と迷っていました。
そこで一旦家に持ち帰って確認してもらうようにしたところ、他の物は手放しやすくなったようです。



思い出の品は一度手放すともう二度と手に入らないから
慎重に選びたいわね。
「終活」として前向きに話す
「片付け」だと抵抗を感じても、「元気なうちに整理しておけば、子どもたちに迷惑をかけない」という言葉には共感してくれる親世代は多いです。
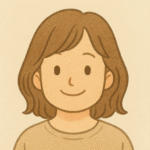
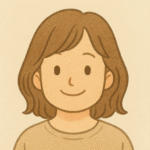
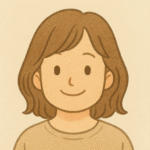
「自分が元気なうちに何とかしないと…」と気にしていた義母も安心し、一緒に片づけができたことで大満足していました。
終活につながる片付けの効果
本人の安心感
片付けを進めることで、「必要なものがどこにあるかすぐ分かる」「暮らしがシンプルで快適になる」という安心感が生まれます。
物が多すぎると探し物ばかりでストレスになったり、つまずいて転倒のリスクにつながったりもします。
必要なものだけに囲まれた暮らしは、心にも体にもやさしい環境になるのです。
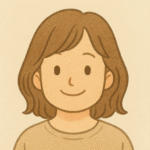
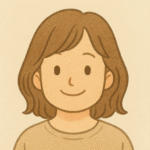
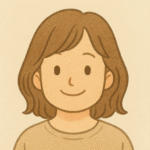
特に高齢者の場合は生活動線の確保が大事です。片付けることで転倒予防にもなりますよ。
家族の安心感
終活の片付けは「自分のため」だけではなく「家族のため」でもあります。
もしものときに家族が大量の荷物を前に右往左往するのは、心身ともに大きな負担。
生前にある程度整理しておけば、「どこに何があるのか」「残してほしい物は何か」が分かるので、残された家族も安心できます。
コミュニケーションのきっかけ
片付けを一緒にすると、「これ、昔こんなことがあってね」と思い出話が自然と出てきます。
普段はできない人生の振り返りや、将来の希望なども話題にしやすくなるのです。
実際、義母と倉庫を片付けているときも、古いアルバムや道具を手に取りながら、義父のエピソードをいろいろと聞かせてもらいました。
それは単なる物の整理ではなく、「心の整理」や「家族の記録」の時間だったように思います。



親父の趣味の工具類が多くて笑っちゃったよね



なんでこんなものが…ってものもあったわね。
ポイント
片付けは「不用品を処分する作業」以上の価値があります。
- 暮らしやすさを整える
- 家族への安心を残す
- 思い出を共有して心をつなぐ
こうした効果を意識するだけで、片付けは「面倒な作業」から「前向きな活動」へと変わります。話しをする時間はとても大切な家族の記録にもなりました。
単なる片付けではなく「心を整理する作業」だったのだと思います。
まとめ
親や義実家の片付けは、「モノを減らすこと」以上に 心に寄り添う姿勢 が大切です。
- 相手の思いを尊重する
- 小さく区切って進める
- 「残したい理由」を認める
- 「終活」として前向きに伝える
この4つを意識するだけで、片付けは驚くほどスムーズになります。
片付けは決して“モノとの戦い”ではなく、家族との対話のきっかけ。
そして未来の安心をつくる大切なステップです。
「片付けたいけど不安…」と感じている方も、まずは小さな一歩から始めてみませんか?
次回は、さらに具体的に 「家族と揉めない片付けの声のかけ方」や「進め方の工夫」 をご紹介します。未来の安心にもつながる大切な一歩。
「片付けたいけど不安…」という方も、少しずつ話題にしていくことで、家族との関係がより良い方向に進むと思います。

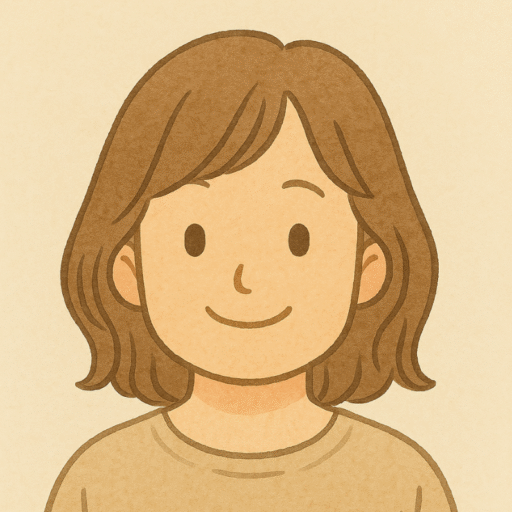







コメント